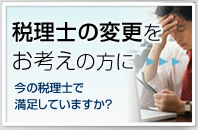税理士事務所内で不正行為を発見した補助税理士等の専門家責任
<目次>
1.税理士の使命と職責
税理士法1条は、税理士の使命について、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」と規定している。
この規定の趣旨として、松沢智教授は、税理士は「いずれにも偏せず税務官庁のみならず、委嘱者からも間を置いて自ら正しいと信ずる法解釈に従って、納税義務者の納税義務を適正に実現させねばならないのである。決して、税務署長の補助機関ではないからであり、このことは、さらに、委嘱者からも、一歩間を置いた関係が求められるのである。そこに独立した公正な立場の意義が現われ、その結果として、「法律家」としての性格が強く表明される 」と指摘する。
しかし、弁護士が「特に対裁判所、対検察庁との関係において、国民の側に立って憲法の基本的人権の擁護を使命 」としている一方、税理士は、税務署長による更正処分に対し、「自ら税法の専門家として、この処分が違法・不当な納税義務の履行の強制であると確信するが故に、それを防止するために行動しているのであって、それは結果として納税義務者の権利を救済することになるが、納税者の財産権を守ることのみで闘っているのではない。税理士は適正な納税義務の実現という租税正義の実現のために行動している 」として、税理士の法律家としての使命を弁護士に準ずるものではないことを主張している。
この点につき、昭和38年12月6日に税制調査会が池田勇人首相に答申した「税理士制度に関する答申」では、「税理士制度の第一義的な意義は、法令に規定された納税義務の適正な実現に資するという点に求めるべきものであると考えられる。しかして、この場合、法令に規定された納税義務の適正な実現に資するためには、税理士が納税者の委嘱を受けて職務を果たしていくその立場は、委嘱者の立場とまったく重複するような形においてではなく、税務会計専門家として見識のある判断を加えるという形において把握されなければならないことは当然であろう 」と指摘した通りである。
しかし、税理士法が規定する税理士の使命については、その役割が拡大されてきていると考えられている。昭和63年5月には、日本税理士会連合会制度部が日本税理士会連合会会長宛に「税理士法第1条に定める税理士の使命のあり方について」を答申しているが、ここでは、「税理士の「独立した公正な立場」を考えるうえでより重要なことは、第1条の税理士の使命全体の理念を通じてこれを理解することである。すなわち、税理士の立場は、納税者に従属した権利擁護ではなく、納税者に対して正すべきものは正すとともに、過大に義務を負わないという見地から、納税者の権利を守り、その利益を正しく擁護するものであることを意味している。したがって、税理士は納税義務を適正に実現するため、憲法に定められた租税法律主義に基づき、税法を遵守して、基本的には納税者の税法上の正当な諸権利を守る立場から対処することが要請されることとなる 」と指摘されていた。
また、平成5年5月には、東京税理士会から日本税理士会連合会に対して「―21世紀へ向けての税理士制度の構想―税理士法改正要綱」が具申されているが、ここでは、昭和55年の税理士法改正案に対する国会審議において「申告納税制度は、国民主権の政治原理に立って主権者たる納税者に自ら租税債務を確定する権能を認めたものです。
したがって、税理士に課せられるべき社会的任務は、必然的にこの納税者の自主申告権である税法上の行為を援助するとともに、税法上の権益を擁護することになる 」との参議院大蔵委員会での発言を引用し、「この税理士の立場は、納税者に従属した権利擁護を意味するものではなく、納税者に対して正すべきものは正すとともに、過大に義務を負わないという見地から、納税者の権利を守り、その利益を正しく擁護するものである 」と指摘していた。
このような方向性が昨今の納税者権利憲章導入論議にも影響を与えている。
2.不正行為の発見に対する税理士の専門家責任
不正行為を発見することは職業会計人の役割として求められているのであろうか。
資本と経営との分離が進み、経営者と株主との理解が対立していく中、「株主監査人には虚偽を看破することができなかった」ことから、「プロフェッショナルの出番」が求められ、専門職業人として勅許会計士が成立していったイギリスの歴史 を鑑みれば、公認会計士については、本来、不正行為の発見が求められるのかもしれない。
日本コッパース事件(東京高裁平成7年9月29日判決、判時1552号128頁)が明らかにしたように、「監査人は、一般に認められた監査基準の下にという範囲内と、監査過程の固有の限界ないに限られるのではあるが、財務諸表に著しい影響を与えるであろう誤謬、不正を発見すべく監査計画を立案し、監査の実施に当たり然るべき技術を駆使し、正当な注意を払うことが可能であり、またそのような手続によって監査を行うことが期待されている」から「本来なすべき手続を怠り、その結果被用者の重大不正行為を看過したときは監査人は、監査の依頼者に対し、それによって生じた損害について賠償すべき責任を負う 」ものとされている。しかし、その責任は第三者に対するものではなく、「監査報告書に虚偽記載をしたことにより第三者が損害を被った場合 」のみである。
一方、税理士の場合は、「証券取引法に基づく責任や商法特例法に基づく特別な責任を第三者に対して負うわけではない 」が、名古屋高裁金沢支部平成9年11月12日判決(判タ974号198頁)のように、取締役である税理士が関係会社に対する無理な資金援助を続ける代表取締役に対して、「税理士として経理についての専門的知識を有していることからしても(中略)新たな資金援助を中止するように助言・忠告すべき職務上の義務が発生していた」と判示している。
また、仙台高裁昭和63年2月26日判決(判時1269号86頁、TAINSコードZ999-0002)は、「被控訴人は、その作成した書類の記載を信用して融資をし、損害を受けたものに対しては、その損害を賠償する義務があるといわなければならないから、控訴人に対し、その作成した書類の虚偽の記載内容を誤信したことにより蒙った前記損害を賠償すべきところ、証拠によれば、控訴人は前記融資を始めたころからA社の取締役になったものであり、A社の帳簿類を閲覧し、その営業実績を調査することができたはずであり、それをしていれば前記確定申告等の虚偽であることを知り得たのに、それをしなかったことが認められ」るとして、取締役である税理士の賠償責任を認めている。
上記事件は、いずれも取締役である会計専門職業人に課された専門家責任の問題であって、「税理士の行う会計業務においては(当然に税務処理においても)不正行為の発見を目的としないから、そもそも不正行為についての報告義務(債務)は存しないとする見解が散見 」すると言われる。「制度上も、法定監査(強制監査)業務は公認会計士や監査法人(会計監査人)が行うことになっており、税理士には帳簿閲覧権や質問検査権が与えられていない」から「税理士は監査について責任は問われない」としても、「『会計業務』を通じて内部不正を発見できた場合にその旨を報告すべきものと考えられる 」ところである。この点につき、「税理士業務の実行過程において不正行為を発見する義務あるいは発見するように努力をする義務は税理士には存せず、また不正行為が行われていることの税理士による通知は損害賠償発生の原因ではなく、損害賠償請求の動機である 」との見解があることには注意する必要があろう。
このような不正行為発見に対する消極的な通説に対し、痛烈な批判がある。すなわち、「職業専門家である税理士は、(中略)適正な納税義務の実現のために(税理士法第1条)、適宜、原始証憑類等との照合を行うことにより正確な会計処理、決算処理及び税務処理が税理士法及び各租税法規により要求されていると解される。(中略)この適正な税額の算定にあたっては、発生している要件事実を正確に会計帳簿、財務諸表、税務申告書に反映する必要がある。税理士業務(及びその前提となる会計業務)、特に税務書類の作成においては、当然に不正行為は排除されるべきであり、(中略)加算税の賦課決定(国税通則法第65条、第66条、第68条参照)や逋脱犯の規定(所得税法第239条等)はまさにこのような不正行為などによる虚偽記載等を厳しく取り締まる趣旨でもある。税理士法第41条の3もこの趣旨である」として、「会計業務それ自体から不正行為を発見できず、虚偽の会計帳簿を作成し、それにより委嘱者に損害を与えたとしても、税理士が債務不履行責任を問われないとする解釈は失当である 」と言うのである。
この点につき、近年の税理士賠償訴訟事件においては、税理士に高度の善管注意義務がある旨を判示する判決が増えている。大阪高裁平成13年3月13日判決(判時1654号54頁、TAINSコードZ999-0018)では、「違法・不当な申告を行うことにより原告が修正申告を余儀なくされたり、更正処分や過少申告加算税の賦課処分を受ける等により損害を受けることのないように指導及び助言をする義務がある。(中略)依頼者の希望が適正でないときには依頼者の希望にそのまま従うのではなく、税務に関する専門家の立場から依頼者に対し不適正の理由を説明し法令に適合した適切な助言や指導をして、依頼者が法令の不知や税務行政に関する誤解等によって生じる損害を被ることのないようにすべき注意義務がある」と判示し、京都地裁平成7年4月28日判決(TAINSコードZ999-0008)では、「指導、助言及び税務申告代行にともなう税務書類の作成の際には、十分に依頼者である納税者の経済活動を把握して、納税者の税務申告が適正に行われ、納税者の財産権等の利害が害されないように配慮し、その事務を遂行しなければならない」と判示する通りである。
ところで、消費税の課税制度方式の適用誤りによって生じた過少申告が否認されたことに対する最高裁平成15年7月18日判決(民集57巻7号52頁)では、「不正な過少申告等にかかわった税理士が申告に係る税額と本来納付すべき税額との差額を依頼者に賠償し、その賠償に係る損害を税理士損害賠償責任保険によりてん補されることによって生じ得る納税申告に係る不正の助長を防止しようとする特約条項の趣旨、目的に反するものではない」と判示しているが、最高裁判決の射程範囲は必ずしも明らかではなく、東京地裁平成12年9月22日判決(金商1134号57頁)のような「税理士の故意・重過失が認められる場合にのみ保険者免責とするという見解に立脚する裁判例」や、「税理士の故意・重過失が認められる場合のほか、不正が助長されるおそれが大きい場合には、特約条項の適用を否定すべきであるとする見解もある」が、「不正が助長されるおそれがあるとはどのような場合であるのか」判断が分かれるため、税務「執行面における不透明性・不確実性を完全に払拭するのは容易ではない」という問題が生じている 。いずれにしても、税理士損害賠償責任保険の免責条項特約の不適用については、不正行為が行われた場合が含まれると解されていることが明らかとなる。
3.補助税理士・業務補助者である税理士の労働者性
一方、税理士事務所における業務補助者の行為に対して、税理士はどのような責任を負うのであろうか。そもそも、税理士が他の税理士を採用した場合、雇用契約が成立するのであろうか。
本件たる東京高裁平成24年9月14日判決は、「控訴人が税理士資格を持つ独自の事業者であり、本格的に事業者としての活動をすることを前提としており、被控訴人は、控訴人を他の従業員と異なる扱いをしていたものといわざるを得ないし、(略)契約は、従来の人的な関係もあり、被控訴人が控訴人の当初の生活を応援するために、被控訴人の税理士としての仕事の一部を任せたという性格が濃いものというべき」であり、「控訴人は税理士であるところ、(略)専門家としての職務の中核部分では、労働契約で予定される指揮命令権とは馴染みにくい面があり、労働契約の認定にはある程度慎重であるべきであること(カッコ内略)から」、控訴人は「雇用契約ではなく、担当顧問先の会計事務等の事務処理のみを内容とする準委任契約」であると判示している。つまり、税理士は、その専門性から自由裁量権が強いので、雇用契約になじまない、という判決である。
ところで、労働契約法は「労働者とは、使用者に使用されて、賃金を支払われる者」(労契2①)と規定し、労働基準法は「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」(労基9)と規定する。つまり、「使用者の指揮命令の権限を予定し、また誠実労働義務を包含する。すなわち、労働契約の合意内容の枠内で、労働の内容・遂行方法・場所などに関する使用者の式に従った労働を誠実に遂行する義務 」を負う者であり、提供した労働力に応じて報酬を得るものである。
請負・委任契約による労務提供の場合、労働者に当たるかは「契約の形式(形態)によって決められるのではなく、労働関係の実態において事業に『使用され』かつ賃金を支払われていると認められれば、『労働者』といえる。『使用され』るといえる典型は、仕事依頼に対する諾否の自由がなく、業務の内容や遂行の仕方について指揮命令を受け、勤務の場所や時間が規律され、業務遂行を他人に代替させえないといった事情がそろう場合である」。
この点に付き、最高裁平成8年11月28日判決は(労判714号14頁)や最高裁平成19年6月28日判決(労判940号11頁)は、自己の危険と計算において労務の提供を行っていることや事業所得として扱われていること等を根拠に労働者性を否定しているが、岡山地裁平成13年5月16日判決(労判821号54頁)、東京高裁平成14年7月11日判決(労判682号72頁)のように労働者性を肯定する下級審判例もある。一方、所得税法においては、給与所得と事業所得の区分を巡る争いとして、最高裁昭和53年8月29日判決(月報24巻11号2430頁)のように、「提供される労務の内容自体が事業経営者のそれと異ならず、かつ、精神的、独創的なもの、あるいは特殊高度な技能を有するもので、労務内容につき本人にある程度自主性が認められる場合であっても、その労務が雇用契約等にもとづき他人の指揮命令の下に提供され、その対価として得られた報酬もしくはこれに準ずるものであるかぎり、給与所得に該当するといわなければならない」と判示される等、前述の労働者性が肯定される場合には給与所得になることが明らかにされている 。
また、「医師、弁護士、一級建築士など高度の専門的能力、資格または知識をもつ者がもっぱら特定事業主のためにその事業組織に組み込まれて、しかし労務の遂行自体については具体的な指揮命令を受けないで独立して労務を供給している場合にも、職務の内容や質量において使用者の基本的な指揮命令の下にあって労務を提供し報酬を得ているという関係にあれば、『労働者』といえる 」と考えられている。
つまり、高度専門能力に基づく他士業においては、自由裁量権が強いから雇用契約になじまない、というのではなく、職務内容や基本的な指揮命令に基づく労務提供である限り、労働者である、と考えられているのである。本件においても、控訴人は、被控訴人の指示による顧問先の会計業務に対して労務提供をしているのであり、自由裁量権があるとはいえ、最終の税務申告を行わない点で、業務補助者に過ぎない。
また、税理士法は、開業税理士や社員税理士が他者の補助税理士になることを禁止しており、会計業務のみの業務以外の税理士業務(ただし、補助業務を除く)を行った場合には、税理士業務を行う事務所が2か所となり、税理士法が禁止する二重事務所の設置に当たることになろう。したがって、本件における控訴人の立場は、税理士行為を自由裁量権に基づいて行い得る立場にない業務補助者に過ぎず、その範囲を逸脱していたならば、税理士法違反を問われることになる。
つまり、税理士資格を有する者が、他の税理士の使用者になるとしても、自由裁量権があるゆえに労働者性が否定されることはなく、雇用者である税理士が業務委託契約に基づき外注処理していることを前提として、控訴人が業務委託に基づき完了引渡しを行った業務に対する報酬を請求する関係であれば、雇用契約ではなく準委任契約ないし請負契約が成立すると考えられるが、雇用者である税理士は、控訴人に対する報酬を給与処理し、控訴人も給与所得として申告し、行った業務の多寡にかかわらず一定の月額報酬を、請求なしに受給することができる関係は、雇用契約に基づくものと考えるのが妥当である。
消費税法において、雇用契約に基づく給与の支給は非課税取引であり、その支給には仮払消費税は発生しないが、準委任契約ないし請負契約に基づく外注費の支払いは課税取引であるから、その支払いには仮払消費税が発生する。被控訴人は税務の専門家である税理士であるから、その事実を知らないはずはない。つまり、控訴人に対する報酬の支払いが準委任契約ないし請負契約に基づく外注費の支払いであると認識していたのであれば、会計処理の時点で当然に消費税を節税可能な外注処理をしているはずであり、給与処理をしてより多くの消費税を進んで納税することはありえない。また、更正の請求の請求期間は、法定納期限から1年内であった(平成23年12月改正で5年に改正)から、平成20年解雇後のトラブルが発生した時点で、消費税の更正の請求を行使していたはずである。いずれも被控訴人において行っていないことからも、税務の専門家たる税理士として、控訴人に対して支給した報酬を、雇用契約に基づく給与であると認識していたものであることは明らかである。
また、福岡高裁昭和63年11月22日判決(税資166号)や平成13年10月31日裁決(TAINSコードF0-1-180)のように、兼業の実態や器具・資材の一部を自己負担で整備していること、請求書・領収書を発行していること、等の非独立的・従属的な労務の提供をしていたとは認められない実態が存在することを踏まえて事業所得と認められた事例も存在する。これは、給与所得性を認定した東京高裁平成20年4月23日判決(税資257号216頁)や、最高裁平成17年1月25日判決(民集59巻1号64頁)が示した判断基準と矛盾しないものであり、所得税法及び消費税法における給与所得該当性の判断基準が、労働法でいう使用従属性と同等のものであることは明らかである。
本件においては、控訴人の被控訴人事務所での会計業務は、被控訴人事務所内に設置された会計システムを用いて業務を行い、業務処理の内容も当然に同サーバー内に保管されるとともに、その会計データは後述の公益通報に至るサーバー内からのデータ抽出が行われるまで被控訴人事務所内サーバーから持ち出されることはなかったのであるから、勤務時間に対する時間的拘束を受けていなかったとしても、場所的な拘束を受けた労働の提供であったことは明らかであり、業務に必要な会計システムは被控訴人事務所より貸与を受けており、また業務の結果としての請求書・領収書の発行は存在しなかったこと、等を踏まえ、さらに、パートタイム労働法制定後の労働環境の変化、フレックスタイム制や裁量労働制の進展を踏めると、基本的な指揮命令系統の下における自由裁量の範囲での労働者性は肯定されることになろう。
4.税理士業務の履行補助者の行為に対する税理士の専門家責任
税理士事務所においても、税理士を採用している場合がこれに当たる。「特に税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に定められた納税義務の適正な実現を図ることを使命とし、公共性の高い税理士業務を独占業務として行うのであるから、いやしくも使用人の行為を通じて納税義務者の信頼を損なうようなことがあってはならない 」。
しかし、資格者たる税理士を業務補助者として採用したのであれば兎も角、無資格者を業務補助者として採用した場合には、業務補助者は税務に関する専門家ではないから、「税理士の使用人等に対する監督義務を税理士法において明示することにより税理士の自覚をさらに促すという趣旨から 」、税理士法41条の2に使用人等に関する監督義務を規定している。
ところが、
この点に付き、大阪地裁平成14年7月26日判決(TAINSコードZ999-0053)は、「被告乙は、原告との間で顧問契約を締結し、決算書類の作成及び税務申告を担当してきた税理士であり、また、被告戊社は、原告との間で顧問契約を締結し、記帳代行業務や法人税の申告に係る事務の補助を行ってきたのであるから、原告に対し債務不履行責任を負い、被告乙の使用人である業務補助者己は、収容等があった日から4年以内に代替資産を取得すれば、圧縮記帳が認められると誤解していた可能性が高く、原告に対しても、本件特例の適用要件について、そのように誤った説明をしたと推認するのが相当であって、原告との間で顧問契約を締結し、記帳代行業務や法人税の申告に係る事務の補助として己を使用していた被告乙及び被告戊社は、説明義務に違反して原告を損害を与えた以上、不法行為責任を負うべきである」と判示し、前橋地裁平成14年12月6日判決(TAINSコードZ999-0062)は、「被告の履行補助者であるCが、原告Aの指示どおりの申告をした場合に、原告らが将来脱税を指摘されて重加算税や延滞税などを課せられる危険があることを何ら説明しないまま、原告Aの指示どおりに所得税等確定申告手続を行ったことは、税務に関する専門家である税理士の立場から、依頼者に対し不適正の理由を説明し、法令に適合した申告となるよう適切な助言や指導をするとともに、重加算税などの賦課決定を招く危険性があることを十分に理解させ、依頼者が法令の不知などによって損害を被ることのないように配慮する義務に違反しており、被告の債務不履行になるといわざるを得ない」と判示する。つまり、税理士事務所において、業務補助者の行為の不法行為責任は使用者である税理士自身に帰属することになる。
しかし、本件判決に基づけば、指揮命令に服し、自由裁量権が与えられていない無資格の業務補助者は雇用契約に基づくものでもあり、使用者である税理士の責になるが、準委任契約に過ぎない補助税理士が行った不法行為責任は、明確な指揮命令に服さず、自由裁量権が強いから、使用者である税理士ではなく、行為者である補助税理士にあるということになる。しかし、この解釈は、業務補助者を含め、法人に参画した者の行為に対する無限連帯責任を課す税理士法人制度の趣旨に反するものであり、税理士法上の解釈を捻じ曲げた解釈と言わざるを得ない。
税理士法ばかりではなく、他士業に比して、税理士に対してのみ、過度に重い専門家責任を課した判決であると言わざるを得ない。
公認会計士監査におけるパートタイム会計士についても、監査主任の指揮命令に服するとはいえ、自己の行った監査業務の結果として監査主任に対して報告をし、自己の発見した
5.公益通報制度・内部告発と税理士の守秘義務
ここまでの検討により、税理士本人が、不正発見に対する高度の善管注意義務を負い、業務補助者の行為による不法行為責任を負うことが明らかとなった。
ところで、税理士事務所内で不正行為が行われていることに気がついた業務補助者はどうすべきであろうか。使用者である税理士が責任を負うことになるのであるから、業務補助者に不正発見のための高度な善管注意義務が課されるわけではないが、職務忠実義務を鑑みれば、使用者である税理士に報告することが当然に求められるであろう。しかし、それで是正されない場合には、公益通報制度や内部告発と守秘義務との関係が問われることになる。
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、納税義務者の信頼に応えて納税義務の適正な実現を図るべく援助をするのであるから、税理士業務の遂行に当たって、納税義務者の資産、負債の状況、資金繰り、取引の内容等々の細部にまで立ち入ることとなり、他人に知られたくない秘密に接する機会が極めて多い。また、納税義務者としても、税理士を信頼し、そうした秘密にかかわる事柄の詳細について真実を明らかにしてこそ、適正な納税義務の実現が図られることになる。納税義務者の秘密に属する事項を税理士がみだりに外部に漏らすおそれがあるとすれば、納税義務者は安んじて税理士に委嘱することはできず、両者の相互の信頼関係は成り立たないことになる 」。それゆえ、税理士法38条及び54条は、税理士及びその業務補助者に対して、在職中、退職後を問わず、税理士業務により知り得た秘密に対する守秘義務を課している。
税務職員の守秘義務 も同趣旨であるが、公務員の告発義務(刑訴239②)にさえ優先する一方、税理士法には告発義務はなく、刑事訴訟法上のできる規定(刑訴239①)でしかないことを鑑みれば、税理士法の守秘義務に関しても、告発義務に優先すべきものと考えられる。
つまり、顧客情報については、告発義務ではなく守秘義務が優先されることになる。このことは、税理士法41条の3が「税理士は、税理士業務を行うに当たって、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知ったときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない」と規定する助言義務をおいていることからも理解されよう。
一方、平成16年、「企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきもの 」であるとして公益通報者保護法が制定されている。「近時の企業経営においては、企業の社会的責任の観点からも、あるいは、甚大な被害を惹起する危険のある様々な訴訟リスク等の回避の観点からも、いわゆるコンプライアンス(法令遵守)経営が求められている。そしてこの要請は、必然的に各企業の業務に従事する労働者にもコンプライアンスを求めることになる 」。「コンプライアンス経営の下では、企業は、企業倫理規程、コンプライアンス規程、あるいは就業規則中に他の労働者等のコンプライアンス違反への企業に対する通報義務を定めていることが多い 」が、このような規定は「法令遵守の徹底のための合理性を有する以上、就業規則の効力が認められ(略)、労働者は、各規定に従った義務を負う 」ことになる。
税理士制度においては職業倫理規定は存在しないが、税理士法1条が「租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命」である旨を規定していることからも、税理士法が、税理士にコンプライアンスを要求していることは明らかである。そして、「違法行為への荷担は、労働契約が前提としている適法・適正・快適な労働環境下で働く権利を侵害するものであることからも 」、コンプライアンス経営が要求される税理士事務所において違法行為がなされている場合には、使用者である税理士にその是正を求めることが第一義的に要求される。
しかし、企業内部への報告というのでは、「仮に中立性・独立性が確保されていれば、組織ぐるみで犯罪が行われている場合でも、長期的にみれば不正を糺すことが企業の利益となるので、適切に行動するインセンティブを持っている筈である。しかしながら、通報受付機関の中立性・独立性が確保されていなければ、通報事実や通報に伴う証拠が握りつぶされる可能性がある。あるいは、通報者の個人情報を通報受付機関の外に流出させ、報復の機会を企業に与える可能性もある。深刻な犯罪行為ほど、それによる企業へのゲインが大きいし、発覚した場合の評判減少などのコストも大きいから、企業としては証拠隠滅行為・報復行為に費用を投入するインセンティブを持つことになる。いったん犯罪行為に手を染めてしまった以上、いわば毒を食らわば皿までという状況になる 」から、公益通報が必要になる。
そこで、守秘義務との関係を考えるに、税理士法は「税理士業務に関して知り得た秘密」(税理士法38)に対する守秘義務を課すのみであり、税理士法基本通達も「依頼人の陳述又は自己の判断によって知り得た事実」(税理士法基本通達38-2)を対象にする旨を規定するのみであるから、税理士事務所内の不正行為については、税理士法が要求する守秘義務の範囲ではないから、刑訴法上の告発できる規定が意味を持つことになろう。
ところで、公益通報者保護法は「具体的には、別表に掲げられた国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する法律違反行為の事実であって、最終的には、刑罰によって、実効性が担保されている法令違反行為の事実が通報対象となる 」が、「問題となるのは、租税関係法と政治資金規正法が含まれていないという点である。内閣府の説明では、専ら国家の機能にかかわる法律であって、『国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる』ものでない、というのが除外された理由とされている。しかしながら、(略)外部から観察困難で、監視が難しい犯罪ほど内部告発が発見および抑止に効果的である。(略)脱税や違法な政治献金などは密行性が高い犯罪であり、こうした犯罪にこそ、内部告発を活用すべき 」である。
しかるに、本件被控訴人税理士Xは、本件控訴人Yが経営するB税理士事務所の業務補助者として、同事務所内で行われていた補助金不正受給の証拠を発見したことから、上司に当たる被告人Yの子息であるCに同案件の是正を要求したところ、是正されないばかりか、被控訴人の税理士登録番号を悪用し、被控訴人Xの関与先ではない控訴人Xの関与先企業に対して、被控訴人Yに業務委託があったことを仮装する等、不適正な税理士行為を行う事態に発展したことから、本件公益通報行為に及んだのであって、後述する補助税理士及び税理士有資格者による業務補助における税理士の専門家責任において、責任解除が果たせない状況に追い込まれたことに対する防衛行為であったといえる。
6.補助税理士の専門家責任の範囲
補助税理士とは、平成13年税理士法改正により創設されたものである。
従来、「親方税理士が委嘱を受けた税理士業務を、何らの手当てをしないまま事務所に勤務する税理士が行うと、納税者から委任されていない税理士が税理士業務を行うことになり、法律関係が不明確になるばかりか、トラブルが生じたような場合の損害賠償責任の問題も起きる虞れもあり、さらには、親方税理士に常時雇用されて、その税理士事務所でほとんど勤務していながら、自宅を事務所に登録しているような税理士の場合、親方税理士の事務所を拠点として税理士業務を行う実態がある一方で、税理士業務の本拠として自宅事務所を登録していることになり、2か所以上の事務所の設置を禁止する規定(法第40条第3項)に抵触することになる。このため、税理士であっても親方税理士の事務所に勤務する税理士は、その勤務先である親方税理士の事務所では税理士業務は行えず、単なる使用人として税理士業務以外の業務しか従事できないと考えられていた 」。
しかし、平成13年税理士法改正により、「税理士となる資格を有する者が、税理士となる」(税理士法18)際、税理士法2条に規定する税理士業務を「税理士が他の税理士又は税理士法人(略)の補助者として」(税理士法2③)「常時(略)業務に従事する者」(税理士法施行規則8二ロ)を補助税理士と規定することによって、親方税理士に事務所に勤務する「税理士が他の税理士又は税理士法人の補助者として、税理士業務を行う 」ことができる補助税理士制度が明文化されたのである。
補助税理士は、あくまで他の税理士又は税理士法人(以下、税理士等)の補助者であるから、業務補助者として使用者である税理士等が委嘱を受けた業務を補助する者であるから、納税者との関係は、使用者である税理士等と納税者との委任契約のみである。したがって、補助税理士は、税務代理(税理士法2一)に伴う税理士の専門家責任を問われることはなく、全責任は使用者である税理士等の責任となる。
しかし、「補助税理士が行う業務は、税理士法第2条第3項に規定されているように、税理士が行う業務であることから、補助税理士自身の名前で税理士業務を行うことになります。具体的には、補助税理士は、従事する税理士等の補助者として自らの税理士証票を提示して税務調査の立会いを単独で行う、あるいは、税務書類を作成し、その作成税理士として、補助税理士自らが署名押印することにより、その身分及び責任の所在を明らかにすることになります 」と指摘されている。
税理士は「納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」(税理士法1)ことから、脱税相談等の禁止(税理士法36)、信用失墜行為の禁止(税理士法37)が規定されている。その上で、財務大臣は、「税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができ」(税理士法45①)、また、「税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる」(税理士法45②)ことになっている。
つまり、補助税理士の専門家責任は、委嘱者である納税者に対してではなく、監督官庁に対する善管注意義務であると解することができる。委嘱者である納税者に対する責任は、税務代理(税理士法2①)に基づいて使用者である税理士等が負うことになるが、補助税理士も税理士であるから、税務書類の作成(税理士法2②)や税務相談(税理士法2③)に関する高度の善管注意義務が課せられているといわざるを得ない。そのため、使用者の税理士とともに補助税理士に対して、納税者からの損害賠償請求事件が提起されてもおかしくはない。
なお、税理士法基本通達は、税理士「法第2条第3項に規定する『補助者』とは、規則第8条第2号ロに規定する補助税理士をいう」(税理士法基本通達2-7)と規定するが、税理士法2条3項には「常時」業務に従事する旨を規定せず、税理士法施行規則8条2号ロは「常時」業務に従事する者を補助税理士と規定することを鑑みれば、税理士法2条3項にいう補助者を補助税理士に限定していないと解すべきであろう。税理士法2条1項が規定する税理士が無償独占する税理士固有の業務については、税理士の二重事務所禁止規定(税理士法40条3項)に抵触するため、補助税理士が税理士法2条3項にいう補助者として業務補助をすることは許されないことは当然である。しかし、税理士法2条2項に規定するいわゆる会計業務に関しては、税理士資格の有無を問わない能力さえあれば誰にでも業務執行可能な業務である。税理士法が「常時」業務に勤務することを求めていない以上、税理士登録者がアルバイトやパートとして「他の税理士又は税理士法人の補助者として」会計業務に従事することは許されると解される。なお、通達のみにより、租税法律関係を変更し、課税要件を変更することは、租税法律主義(憲84)に反し、許されないことは当然である。
この場合の業務補助者たる税理士の専門家責任は、一般の業務補助者と同様となると考えられなくもないが、税理士と名乗るかどうかの問題ではなく、税理士であることによる専門家責任であるから、やはり、補助税理士と同様、高度の善管注意義務を負うことになろう。
しかるに、本件控訴人税理士Xは、訴外税理士法人Aの代表社員であり、被控訴人Yが経営するB税理士事務所の補助税理士ではなく、会計業務のみに関する業務補助者であった。税理士法人は合名会社と同様、無限責任社員のみにより構成され、「税理士法人の社員は、自己若しくは第3者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員と」(税理士法48の14)なることを禁じている。したがって、控訴人XはB税理士事務所において補助税理士として業務をすることは許されないところ、訴外A税理士法人は税理士法2条1項の業務のみをその業務としていることから、B税理士事務所において会計業務の補助者としてパート勤務することは禁じられていない。
ところが、B税理士事務所は、控訴人Xの税理士登録番号を悪用し、控訴人に許されていない被控訴人事務所における税理士法2条1項の税理士業務を行っているかのような外形を仮装し、控訴人Xが明確な税理士法違反を行っているかの外形を創出する等、控訴人Xの不利益行為を行うばかりか、控訴人Xの専門家責任としての高度の善管注意義務に基づき、発見されたB税理士事務所内における不正行為の報告に対しても、不誠実な対応をとり続けたが故に、控訴人Xは税理士法上の自己の責任を回避するために、仕方がなく税理士会、国税庁等に公益通報せざるを得なくなったものと推認されるところである。
また、B税理士事務所の実体は被控訴人Yの息子たち(税理士資格を保有していない)がYの名義を借りて経営されているものであり、税理士法が禁止する名義貸しに近い状況であったことも注意せざるを得ないところである。