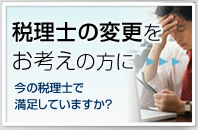IFRSアドプションと確定決算主義
―大企業優遇税制からの脱却の可能性― 税理士 平 仁
1.問題提起
平成21年6月30日に企業会計審議会がまとめた「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」(以下、中間報告)は、「IFRSを一定範囲の我が国企業に強制適用するとした場合の道筋を具体的に示(※1) 」すべきであるとして、それまでの「コンバージェンス(収斂)」から「アドプション(採用)」へシフトした。
わが国の法人税法は、所得計算を公正妥当な会計処理の基準(法税22④)に求めるが、時価主義を旨とするIFRSと法的な権利確定を要件とする法人税法とは考え方が全く異なり、法人税法は別段の定めを置くことで国際的調和を図るための会計基準改正に対応してきた。また、法人税法が「企業会計の考え方と両立しない損金算入を認める場合には、企業会計上も同様の取り扱いをすること(略)をその条件とすることが多い(※2)」ため、IFRSをそのままわが国の会計基準に採用することは、確定決算主義(法税74①)に抵触する可能性が高い。そこで、本稿では、IFRSがわが国の会計基準に採用された場合に、法人税法上の確定決算主義の観点からどのような弊害が生じるかを検討し、IFRSアドプションが税法に与える影響を明らかにする。
2.IFRS適用は連結のみか
中間報告が「我が国固有の商慣行や伝統的な会計実務に関連の深い個別財務諸表に先行して機動的に改訂する考え方(いわゆる「連結先行」の考え方)で対応していくことが考えられる(※3)」としたことから、IFRS適用は連結のみであると誤解されているが、「上場企業は、少なくとも連結先行期間において、IFRSに基づく連結と日本基準に基づく個別を資本市場向けと会社法の開示規制向けに作成・開示しなければならなくなる。また、個別もいずれIFRSに基づいて作成されるようになる(※4)」。
一方、平成22年4月、経産省企業財務委員会は、「会計の国際化は上場企業の連結財務諸表に限定して議論されているのであって、単体(個別財務諸表)についてのコンバージェンスは国際的に要請されているものではないことを確認しておく必要(※5)」があり、「非上場企業の財務情報について、我が国の主権が及ばず、絶えず変化を続けるIFRSの影響を遮断すべき(※6)」であるとして「非上場企業については会計の国際化の議論の範疇外であることを明確にする必要(※7)」があるから、連単分離を確立すべきである旨を明らかにした。
企業財務委員会は、連単分離により非上場会社の会計にはIFRSの影響を排除すべきとするが、我が国の商法、会社法は会社を上場、非上場により区別していないことから、何らかの立法措置が必要になってくる可能性が高い。
3.公正なる会計慣行
昭和49年改正により旧商法32条2項が創設され、公正なる会計慣行に従った会計処理が商法上でも確認された。さらに、「国際的にも信頼性の高い基準に従った計算書類の作成が重要性を増し(※8)」、「最新の会計基準と商法の計算関係規定に齟齬を生じないように、積極的、かつ、迅速な商法改正(※9)」が行われていることから、平成18年会社法制定により、「公認会計士監査がその拠り所とする企業会計原則を中心とする会計諸規則に商法上の根拠を与え(※10)」ることになった。会社法制定に伴い改正された規定が会社法・商法とも同一の文言であることを鑑みると、商法上の公正なる会計慣行は、会社の規模の大小や上場・非上場に関わりなく、同一のものが適用される。
ところが、IFRSをコンバージェンスする場合には日本基準が残存されるが、会社法431条が「商法上の監査と証券取引法上の監査とを一元化し、その円滑な実施を図るために、商法と証券取引法上の会計基準が一致し、同一の会計基準に従って監査が行われることを明確にする目的でもうけられた(※11)」規定であるため、IFRSと日本基準のダブルスタンダードは立法目的に反する。
一方、IFRSをアドプションするとなると、日本基準をIFRSと一致させるから、IFRSが商法上の公正なる会計慣行に該当することになる。
会計基準の設定方法を巡って、原則主義の考え方と細則主義の考え方がある。「基準設定において抽象的な包括規定に焦点を置くのが原則主義であるのに対して、具体的詳細規定に焦点を置くのが『細則主義』である。(略)『真実かつ公正な外観(true and fair view)』の大原則に立つイギリスの会計基準とその影響の強いIFRSは原則主義指向であるのに対して、訴訟防衛が強いアメリカ会計基準や大陸法の詳細規定を伝統にもつ日本基準は細則主義指向といえる(※12)」。「日本(や米国)は『法や基準に書いてあることをすべて順守すれば、財務報告の目的は達成される』といった理解をする(略)細則主義を採る」から、「法や基準には細かなことまで書かざるを得ない(※13)」ことになる。つまり、細則主義を旨とする我が国の法規範とIFRSとは矛盾する。
租税法においては、租税法律主義(憲84)が要請されるが、「侵害規範としての租税法の特質を考慮すれば、租税法が課税要件を法律以外のもの(略)に委任するということは考えられない。課税要件法定主義や課税要件明確主義をその内容とする租税法律主義からして、全く受け入れられない(※14)」。我が国の内政が関与しない国際ルールに過ぎないIFRSに租税法の法規範性を担わせることはあり得ない。
4.確定決算主義と損金経理
我が国の法人税法は、確定決算主義(法税74①)を採用している。確定決算主義とは、「原則として、損金経理を条件として、株主総会の承認または社員総会の同意その他これに準ずる機関の承認を受けた決算上の確定決算利益を基礎として、それに税法上の規定により修正して課税所得を誘導計算しようとする考え方(※15)」を言う。確定決算主義が採用される理由として、「課税の簡便性ないし便宜性が得られる(※16) 」こと、「課税所得の計算上、確定した決算に表明された企業の意思を重視することにより計算の信頼性ないし客観性を担保し、もって課税の安定ないし法的安定性を得ることができること(※17)」等が挙げられる。
法人税法74条が「確定した決算」に基づく申告を要求するのは何故であろうか。判例が株主総会決議による承認を受けていない申告書の効力を否定しないのは、「確定決算とは、法人税法上の税務調整を加えることによってのみ、直ちに、確定申告の内容を形成しうる程度に確定性をもつものとして作成された決算、という実体法的な概念であって、単に株主総会の承認・総社員の同意その他の手続による承認を得た決算というような、形式的な概念ではない(※18)」。「したがって、実質的に法人の意思により租税目的のために租税法律に従って確定された決算に基づいた納税申告であれば、法人税法上必ずしも不適法となるとはいえない(※19)」のであり、税法基準の優位性が示される。
法人税法の課税所得計算は単一の帳簿に基づいて、法人税法の目的に従って申告調整していることが明らかである。しかし、帳簿自体が単一であるが故に、損金経理が要件として課されている場合には、税法上の優遇措置を得ることを目的として税法が記帳基準として採用される逆基準性の問題が生ずる。それゆえ、「税法と商法(会社法)およびその他の法律とを同一会計制度のなかで実践した場合、とりわけいわゆる確定決算主義を採用した場合には、その法理念に基づいた企業の実態を、正確に財務諸表にディスクローズすることが不可能となる(※20)」。これでは、IFRSをアドプションする意味が失われる。
5.租税特別措置の合理性
課税の公平を図るため租税公平主義(憲14①)が要請されるが、「すべての所得を課税の対象とすることには、例えば、二重課税の防止や、政策的な見地から課税とすることが不都合な場合が少なからずある(※21)」ため、各種の租税特別措置が設けられる。 租税特別措置の性格について、「租税特別措置は、一定の政策目的を達成するための手段として租税のインセンティブ効果を活用しようとするものであって、経済政策の一環としての意義をもつものであるが、その反面、負担公平原則や租税の中立性を阻害し、総合累進構造を弱め、納税道義に悪影響を及ぼすなど、多くの短所がある点にかえりみ、当調査会が従来から答申してきた整理縮減の方向を引き続き推進すべきもの(※22) 」と答申されるように、暫定的な特例措置である。これが不合理な優遇であるかどうかを判断する上で、「①その措置の政策目的が合理的であるかどうか、②その目的を達成するのにその措置が有効であるかどうか、③それによって公平負担がどの程度に害されるか(※23)」等を検討する必要がある。
6.まとめに代えて ―大企業優遇税制の終焉―
法人税法上の公正処理基準や確定決算主義を支える損金経理要件は逆基準性を生むが、税法基準により影響を受ける従来の日本基準からIFRSへ全面的に移行するアドプションでは、逆基準性は完全に排除されることになる。IFRSをアドプションした会計基準に基づいて公認会計士監査が実施されることになるが、税法上の優遇措置を利用するための損金経理を行った場合には、公認会計士はIFRSに準拠していない会計処理に対して適正意見を表明することができない。そして、租税特別措置の多くは、損金経理要件が課されているため、公認会計士監査を受忍する大企業・上場企業は、租税特別措置を利用することが許されない。したがって、租税特別措置はIFRSにより影響を受ける可能性が小さい中小企業にのみ利用可能な制度となる。つまり、従来型の大企業優遇税制は採用不可能となる。
IFRSをアドプションするということはIFRSに基づいた記帳を必要とする。アドプションに当たり損金経理要件を緩める場合「法人税法として何か客観的な基準を提示するということが必ず伴ってくる(※24)」。しかし、これはコンバージェンスである。したがって、我が国の法体系に大変革をもたらすことなくIFRSを導入するためにはコンバージェンスしか方法はない。大企業・上場企業は、損金経理要件の緩和・排除がなされなければ、IFRSに準拠しない税法基準が公認会計士監査によって排除されることになるため、大企業・上場企業は租税特別措置を利用することが不可能になる。
参考文献
- 企業会計審議会「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」(2009)、14頁
- 金子宏『租税法〔第15版〕』弘文堂(2010)、34頁
- 企業会計審議会、前掲注1、3頁
- 徳賀芳弘「国際財務報告基準への日本の対応-トライアングル体制変更の可能性-」別冊税務通信『最新IFRS完全詳解』(2010)、3頁
- 企業財務委員会「会計基準の国際的調和を踏まえた我が国経済および企業の持続的な成長に向けた会計・開示制度のあり方について」(2010)、6頁
- 企業財務委員会、前掲注5、6頁
- 企業財務委員会、前掲注5、6頁
- 相澤哲・岩崎友彦「株式会社の計算等」相澤哲編『立案担当者による新・会社法の解説』別冊商事法務295号(2006)、122頁
- 相澤・岩崎、前掲注8、122頁
- 拙稿「青色申告制度の帳簿要件」国士舘法学38号(2008)、84頁
- 森田哲彌、岡本清、中村忠『会計学大辞典[第4版]』中央経済社(2007)、353頁
- 古賀智敏「投資者保護法制の展開と会計理論の変容」安藤英義・古賀智敏・田中健二編『体型現代会計学第5巻企業会計と法制度』中央経済社(2011)、163頁
- 田中弘『国際会計基準(IFRS)はどこへ行くのか』時事通信社(2010)、161-162頁
- 末永英男「税務会計の現状と課題」安藤・古賀・田中編、前掲注12、269頁
- 柳裕治「税務会計研究における確定決算主義」安藤・古賀・田中編、前掲注12、300頁
- 坂本雅士「会計基準の国際的統合化と確定決算主義」『税務会計研究会報告 企業会計基準のコンバージェンスと会社法・法人税法の対応』日本租税研究協会(2010)、109頁
- 坂本、前掲注16、109頁
- 柳、前掲注15、309頁
- 柳、前掲注15、309頁
- 柳、前掲注15、317頁
- 酒井克彦『フォローアップ租税法』財経詳報社(2010)、32頁
- 政府税制調査会「昭和39年度政府税制調査会答申」(1963)
- 金子、前掲注2、82頁
- 岩崎政明(司会)・坂本雅士・品川芳宣・成道秀雄・渕圭吾・吉村政穂「パネルディスカッション 企業会計基準のコンバージェンスと会社法・法人税法の対応」、税務会計研究会報告、前掲注16、50頁(吉村発言)
| レポート・刊行物 目次へ |