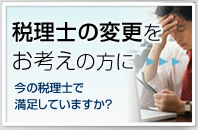居住用財産の特別控除―共有家屋の一部を取り壊してその敷地を譲渡した場合―
(東京高裁平成22年7月15日判決、判時2088号63頁、TAINSコードZ888-1538)
<争点2>
東京高裁平成22年7月15日判決
<認定事実>
控訴人は、平成18年3月10日、小田原税務署長あてに「本件確定申告書」を提出したが、その際控訴人は、本件譲渡に係る長期譲渡所得の金額を1613万3655円、納付すべき税額を210万0600円と記載する一方で本件譲渡について、本件特別控除の適用を受けようとする旨の記載をしなかったことが認められる。
そこで、控訴人について、措置法35条3項が規定する「やむを得ない事情」があったといえるかについて検討する。
措置法35条3項が規定する「やむを得ない事情」とは、天災その他本人の責めに帰すことができない客観的事情があって、居住用財産の譲渡所得の特別控除の制度趣旨に照らし、納税者に対して、その適用を拒否することが不当又は酷となる場合をいうものと解するのが相当である。
これを本件についてみると、証拠及び弁論の全趣旨によれば、控訴人は実弟である戊とともに、本件確定申告書を提出するに際して、再三にわたり小田原税務署を訪れ、担当官に対して、措置法35条1項の適用を望む旨伝え、これが認められるかどうかについて相談したが、小田原税務署からは、いずれの相談に際しても、本件は建物の一部譲渡であるから認められないとの回答がなされたこと、控訴人は、戊を通じて、本件の補佐人である林税理士とも相談したが、本件については、判例も前例もない難解な問題であるとのことであり、後に処分を受けて加算税を課せられた場合のリスクは大きいと考え、本件の特別控除を適用しての申請を断念したこと、しかし、その後に林税理士から、法律の解釈が不明であるために加算税が課せられることを避けるために税務署の見解に従った申告をせざるを得なかった場合にも、1年以内であれば更正の請求を行うことができるとの助言を得て、平成18年12月27日に小田原税務署長に対して更正の請求をしたことが認められる。
本件譲渡に本件特別控除の適用があるといえるかについての判断は2で述べたとお りであって、原審と当審は判断を異にするものである。このような本件における法律解釈の難しさに加え、上記のような控訴人が本件譲渡について更正の請求をするに至った経緯に照らすと、控訴人が、本件特別控除の適用を受けようとする旨を記載した確定申告書を提出しなかったことについては、措置法35条3項が規定する「やむを得ない事情」があったと認めるのが相当である。
検討
本件は、<争点1>共有物であった1の建物の一部を取り壊し、その敷地の用に供されていた土地を分筆した上で、取り壊した建物の用に供されていた土地を更地として売却した場合に、措置法35条1項の特別控除を用いることができるのか、<争点2>確定申告要件である特別控除を用いるに当たって、税務当局から否認される危険性が高い場合に、更正の請求によって特別控除を用いることが許されるのか、という2つの争点について争われた事例である。
<先行事例>
(1)最高裁昭和57年9月30日判決(TAINSコードZ127-5078)引用は東京地裁昭和54年11月19日判決(行裁例集30巻11号1884頁、TAINSコードZ109-4502)
措置法35条1項は、個人がその居住の用に供している家屋とともにその敷地の用に供している土地の譲渡をした場合の譲渡所得について特別控除を認めているが、その趣旨は、右のような居住用財産の譲渡によって住居を失った場合には、これに代わる新たな住居を取得しなければならなくなるのが通常であることを考慮して、右譲渡による税負担をできるだけ軽減しようとしたものである。このような立法趣旨からすると、個人が、その居住の用に供している家屋を、その敷地の用に供している土地を更地として譲渡する目的で取り壊した上、当該土地のみを譲渡した場合には、家屋を敷地とともに譲渡した場合に準ずるものとして措置法35条1項に該当すると解するのが相当であり、更にそれにとどまらず、本件のように、個人が、その居住の用に供している家屋の敷地の一部を更地として譲渡するために当該家屋の一部を取り壊し、その取壊部分の敷地を譲渡した場合にも、右取壊しが敷地を更地にするために必要な限度のものであり、かつ右取壊しによつて残存家屋が居住の用に供し得なくなつたときは、これに代わる新たな住居の取得を必要とすることになるのであるから、右譲渡につき措置法35条1項を拡張適用する余地があるものと解される。
本件土地売却の際の一部取壊しによつても、本件家屋は居住者である原告及びその母の居住の用に継続して供し得たものであり、原告らが転居したのは、本件家屋が居住の用に供し得なくなつたためではなく、本件残地をA社に賃貸し、原告らの入居するビルを建てるための準備としてなされたものと認めるのが相当であり、この認定を覆すに足る証拠はない。
(2)京都地裁平成3年10月18日判決(判タ774号161頁、TAINSコードZ186-6789)
認定事実によれば、本件建物は、もともと構造的にみて日常生活を基本的に営むための水道設備、台所、風呂等もなく、母屋の付属建物として母屋と一体で利用される構造を有し、物理的に一体性があり、実際にも、本件建物は母屋の付属建物として買い入れ、以後原告やその子供らの家族が入れ替わり住居として利用してきた経緯があり、また、原告は長女Aの夫Dに生計を依存し、原告とDの生計は一体であつたこと、原告は、母屋を利用せずに本件建物で独立して生活していたとは到底考えられず、D及びその家族が母屋に転入した昭和54年4月3日以降、同人らが母屋から転出した昭和59年6月3日までの間も含め、その前後を通じ終始母屋を利用していたことなどを考え併せると、本件建物は構造上利用上母屋と一体となつたその付属建物であつて、これが原告主張のように、母屋と独立した居住用家屋であるとの事実が認められないことが明らかであり、右主張に副い本件建物と母屋は当初から、或いは途中からベニヤの壁で仕切られていたとか、原告はもともと独立した建物に居住していて、これを出て他人に賃貸していた独立の家屋である母屋を明け渡して貰つてこれに入居したという原告本人尋問の結果の一部は各証拠、弁論の全趣旨に照らし遽かに措信できず、他にこれを認めるに足る的確な証拠がない。
証拠を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定に反する証拠がない。(1)母屋には、もともと関西電力のメーターが設置され、実際に使用されており、電気設備があつた。(2) 母屋には、従来から水道設備があり、水道が使用されていた。(3) 原告は、昭和56年から同57年にかけて母屋を改造し、母屋には、洗面所、便所、浴室等がある。右認定事実によれば、母屋にはもともと基本的日常生活を営むに必要な設備が整つていたことが認められること、さらに、事実によれば、原告及びA、あるいは原告の次男C及びその家族は本件譲渡後に、残存する母屋に居住しているのであるから、残存した母屋は本件譲渡によつて、何ら生活上の機能を失われなかつたことが明らかであるから、母屋はもともとそれだけで、独立した生活機能を有する居住用の家屋であり、本件譲渡後もその機能を維持していることが認められる。
先行事例を検討するに、<争点1>については、居住用財産を譲渡した場合には、通常新たに居住用代替資産の取得がなされること、通常の居住用財産であれば特別控除額の範囲内で居住用代替資産を取得できると考えられること、を考慮した措置法35条1項の立法趣旨に即して、居住用財産の一部を取り壊した結果、残存家屋が居住の用に供さなくなった場合には、一部取り壊しにより更地にした居住用に供されていた土地の譲渡に措置法35条1項の特別控除を用いることができる、と考えられてきたものといえる。
本件では、原告と己との共有財産であった本件建物のうち、原告が居住する部分に当たる、原告が相続により取得した持分1/4を取り壊すとともに、原告から持分1/4を己に贈与した場合に、残存家屋に己及びその家族が居住しているから、先行事例から判断すれば、措置法35条1項の特別控除の適用はないものと考えられる。
しかし、原告は自己の居住する居住用財産を取り壊して更地にして譲渡した上で、自己の居住用代替資産を取得しているのであるから、原告の居住の実体からすれば、措置法の立法趣旨に合致した状況にはある。
地裁は、従来からの先例に従い、居住用資産の一部が取り壊されたとはいえ、残存家屋が居住の用に供し得ない状況になっていないことを鑑み、措置法35条1項の特別控除の適用はないものと判断した。措置法35条1項が「政策税制である」から、「本件のように家屋の一部取壊し、土地の譲渡後も残存部分で居住を継続できる場合にまで本件特例を認めることは妥当ではなく、判示は妥当である(※1)」とも考えられる。
しかし、先行事例(1)が判示したように、措置法35条1項の適用に拡張解釈の余地を残しているのは、「『居住用財産の処分は一般の資産の譲渡に比して特殊な事情にあり、担税力が弱いことなどを考慮する』という同条項の趣旨にあることは明らかであり、かかる趣旨を徹底させれば、『一連の行為の結果、自己の所有する住居を失い、新たな住居の取得の必要性が生じたかどうか』により本件特別控除の適用の有無を判断するというXの主張も一理あるように思える。しかし、裁判所としては、措置法35条1項の規定を空文化するようなかかる解釈を採ることには抵抗があったのではないか。そこで、控訴審裁判所は、自ら判示するように、『限定的な要件のもとで』、措置法35条1項の適用を余地を認め、同条項の適用の範囲に一定の限定を付した(※2)」と捉える向きもある。
控訴審判決は、認定事実において「被控訴人は、本件建物取毀しに関する合意の成立を争っているが、上記認定の控訴人と己の本件建物一部取り毀しに至るまでの本件建物での居住の実情とその経緯、本件遺産分割の内容、さらに、実際に本件建物が己の居住部分を除いて取り壊され、控訴人が本件建物から転居するに至った経緯に照らすと、本件合意がなされたとみるのが当事者の合理的意思解釈として素直な見方というべき」であり、「本件合意の趣旨からすると、当事者の合理的意思解釈としては、本件建物の一部取り毀しに際しては、その部分に対する己の共有持分の放棄がなされることとの見合いで、残存家屋部分に対する控訴人の共有持分の放棄がされることが合意されていたとみるべきであり、贈与ではなく放棄としたほうが権利の実体に沿うものである」と事実認定しており、事実認定において、原告が共有物件の持分を放棄し、自己所有部分のみを取り壊し、その居住の用に供していた土地を譲渡したものと認定したことによって、残存家屋には原告の持分はなく、原告の居住の用に供されていないから、措置法35条1項の適用の余地があるとした、判決の射程距離が限定される事例判決として判示されたものと考えるべきであろう。
また、<争点2>については、画期的な判決であるといえよう。「本件における法律解釈の難しさに加え、上記のような控訴人が本件譲渡について更正の請求をするに至った経緯に照らすと、控訴人が、本件特別控除の適用を受けようとする旨を記載した確定申告書を提出しなかったことについては、措置法35条3項が規定する「やむを得ない事情」があったと認めるのが相当である。」との判示は、法解釈の困難性により、依頼者である納税者に不利益を与えることなく、納税者の意図する納税行為を実行する上で、「更正の請求の使い勝手は良くなった(※3)」と評価できよう。「しかし納税者の事情は、裁判所も指摘するように、『しばしば見られる』日常的な話であるにもかかわらず、納税者の負担が控訴審まで継続した事実は重い(※4)」のであり、問題の早期解決を図るためにも、不服申立制度の改正が急がれるところである。また、本件においては、4度にわたり税務署に相談する等の行動がなされているが、文書回答制度を効果的に用いる必要性が高かった事例であったともいえよう。
参考文献
- 村野清文「居住用家屋の一部を取り壊し、その敷地の用に供されていた土地を譲渡した場合に租税特別措置法35条(居住用財産の譲渡所得3000万円特別控除)適用を認めなかった事例」RETIO78号(2010)、133頁
- 橋本浩史「同一建物に居住しその敷地を共有する者の間で、土地建物を分割し、一方が分割取得した建物部分を取り壊し、その敷地部分を第三者に譲渡した場合において、租税特別措置法35条1項の適用が認められた事例」税経通信2011年2月号(2011)、198頁
- 後藤健吉「共有家屋の一部を取り壊して敷地譲渡した場合に特別控除の適用はあるか?特別控除の適用を受ける旨の記載をしなかったことが、「やむを得ない事情」に該当するか?」税理士界1278号(2011)、15頁
- 林仲宣・谷口智紀「居住用財産の特別控除」税務弘報59巻3号(2011)、69頁
| 前へ | 1 2 3 | レポート・刊行物 目次へ |