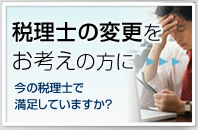臨時特例企業税条例事件(最判H25.3.21)(2)
東京高裁平成22年2月25日判決(判時2074号32頁) 原判決取消
1.地方公共団体の課税権
憲法は、92条においても94条においても、地方公共団体の権能等を法律をもって具体化するものとしており、法律を条令の上位に置き、条例は法律の範囲内でのみ制定することができるものとしている。これは、地方公共団体に自治を認めるにしても、その基本となる事項については、国家的な観点からの調整が必要であるとの考え方に基づくものと考えられる。とりわけ、租税の賦課については、国税を含む国民の総合的な税負担の在り方、国、都道府県及び市町村間ないし各地方公共団体相互間の財源の配分等の観点から、国家的な調整が不可欠であるから、租税に関する条例も、憲法の規定に直接基づくのではなく、法律の定めるところにより制定されるべきものとされているのであり、条例は法律の定めるところにより制定されるべきものとされているのであり、条例は法律の定めに反することはできないと解すべきである。即ち、憲法により認められた地方公共団体の課税権は、あくまでも抽象的なものにとどまり、法律の定めを待って初めて具体的に行使し得るものというべきである。
2.徳島市公安条例事件判決との関係
法律は、明文の規定に示していなくても、あるいは、明文の規定に示したほかにも、解釈上、ある事項を命じていたり禁じていたりすることがあることは、いうまでもないところである。したがって、条例が法律に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言とを対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない(最判S50.9.10徳島市公安条例事件)。
地方税法が明文で禁じていなくても、条例による規制を禁止している趣旨である場合には、条例は同法に違反することになる一方で、条例が同法とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって同法の規定の意図する目的と効果を何ら阻害することがない場合や、同法が必ずしも全国一律同内容の規制をする趣旨ではなく、各地方の実情に応じて別段の規制を付加することを容認する趣旨である場合等には、条例は同法に違反しないことになる。
3. 地方税法による法定外普通税の位置づけ
地方税法は、道府県の課する普通税を網羅的に規定することをせずに、国家的な調整が必要な税目を選別した上で、全国一律に課すべき地方税及び課すことは任意でも課す以上は同一の内容となるべき地方税を列挙するとともに、付加的に各地方公共団体がそれぞれの裁量に基づいて普通税や目的税を課すことを許容し、それらについては総務大臣の同意を通じての調整にとどめる立法政策を採っていることができる。 もっとも、法定外普通税は法律に違反する内容とすることができないことは、いうまでもないから、地方税法の定める法定外普通税の規定に違反する内容の法定外普通税を定める条例は、違法無効となるといわなければならない。
しかし、そのことから直ちに、趣旨、目的は法定普通税と近似しているが、課税客体あるいは課税標準を異にする法定外普通税までが、許されていないというのは、論理に飛躍があり、これが同法により一般的に禁じられているというべき根拠は見いだせない。
4. 法定外普通税の新設等についての総務大臣の同意
地方税法259条〜261条は、道府県法定外普通税の新設等につき、総務大臣に協議した上で、その同意を得なければならないこととし、その手続、要件等を定めている。このように、道府県は、総務大臣の同意を得ない限り、法定外普通税の新設等をすることができないが、この同意を得たからといって、その法定外普通税が適法なものであるとされたことにはならず、法定外普通税の適法性が裁判所の審査に服することは、いうまでもない。 総務大臣は、本件の企業税創設の同意に際して、「法人税法の規定に基づく欠損金の繰越控除制度は、国の租税施策である法人税の制度の重要な構成要素であり、「国の経済施策」に含まれるものである。」とした上で、本件条例が同号に該当しないと判断していたものであり(甲44)、同法の規定が「国の経済施策」に含まれるとの解釈の下に適法性の審査を行ったと認められる。
法律の定める税目の課税標準それ自体を条例で変更することは、法律がそれを許容している場合以外は、許されないことは、いうまでもない。改正前地方税法72条の19は、法人事業税の課税標準を一定範囲で変更することができるが、それを超えて変更することは許されない。また、改正後地方税法はこの規定を削除したので、法人事業税の課税標準を条例で変更することは、一切許されなくなった。
したがって、仮に本件条例が、法人事業税それ自体の課税標準を変更するものであるならば、それは許容されないことになる。
5. 道府県法定外普通税の非課税の範囲に関する規定
この規定は、明確に課税を禁ずる規定なので、条例により同号所定の事業や収入に課税することは許されない。
6. 地方税法の法人事業税に関する規定の検討
改正前地方税法は、法人事業税の原則的な課税標準を「所得」と定め、その計算上繰越控除を認める規定を置く一方で、「事業の情況に応じ」、地方公共団体の判断により、「所得」によらず「資本金額、売上金額、家屋の価格、従業員数等」を課税標準とすることを認めていた(72条の19)。
これによれば、例外的ではあっても、地方公共団体の判断によって、繰越欠損金を控除すれば「所得」が0円ないしマイナスになる赤字法人であるにもかかわらず、その意味においては担税力がないというべきであるにもかかわらず、資本金額、売上金額等の外形を標準に法人事業税を課税されることになるものが出てくることも、また、その点において法人事業税の課税標準が全国一律同一にならないことになっても、やむを得ないと考えているということになる
。 そうすると、同法は、法人事業税について、欠損金の繰越控除が全国一律に必ず実施されなければならないほどの強い要請であるとまで考えていないといわざるを得ない。ましてや、同法が、法人事業税においては原則として欠損金の繰越控除により課税をしないものとしている控除前の利益について、別の税が課税されることを強く拒否していると解さなければならない理由があるとはいい難い。
欠損金の繰越控除を永続的に一切認めないことまでは、その性質上許容されるかどうかに疑問が生ずるとしても、少なくとも時限的に全く認めない制度を創設することも、許容されるというべきである。したがって、所得の計算上欠損金の繰越控除を認めないことをもって、過重な課税であるがゆえに違法であるということはできない。 法人事業税は益金から欠損金を繰越控除した所得に担税力を見いだして課税するものであるとしても、そのことから、欠損金を繰越控除する前の益金に担税力を見いだして別の課税を行うことが否定される理由はないし、地方税法の法人事業税に関する規定がそこまでのことを規定していると解さなければならない必然性はない。
7. 本件条例の規定、制定の趣旨等についての検討
企業税は、「県の行政サービスを享受し、かつ、当該事業年度において利益が発生していながら、欠損金の繰越控除により相応の税負担をしていない法人に対し、担税力に見合う税負担を求める」ことを趣旨、目的として「当該事業年度に生じている利益に対して課税する」ものとして創設されたことが認められる。そして、このような趣旨、目的の普通税は、理念としては応益性を考慮しながら課税標準の選択においては応益性をほとんど取り入れていない法人事業税とは別個の、より応益性を重視した性格を有する税目として成り立ち得るものと解される。
そうすると、企業税は、単に法人事業税と異なる外形を整えただけのものではなく、法人事業税を補完する「別の税目」として併存し得る実質を有するものというべきである。
最終報告書にいう「繰越欠損金控除の遮断」は、最終的に整理された法定外普通税の創設の動機となったものであり、企業税の実際上の効果を分かりやすく端的に示した言葉にすぎず、これを根拠にして、企業税が法人事業税の課税標準等を変更しようとする実質のもの、あるいは法人税法の規定を逸脱するものとまで言わなければならないとは解し得ない。
最高裁平成25年3月21日判決 原審破棄自判
(2)憲法は、普通地方公共団体の課税権の具体的内容について規定しておらず、普通公共団体の組織及び運営に関する事項は法律でこれを定めるものとし(92条)、普通地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定できるものとしていること(94条)、さらに、租税の賦課については国民の税負担全体の程度や国と地方との間ないし普通地方公共団体相互間の財源の配分等の観点からの調整が必要であることに照らせば、普通地方公共団体が課することができる租税の税目、課税客体、課税標準、税率その他の事項については、憲法上、租税法律主義(84条)の原則の下で、法律において地方自治の本旨を踏まえてその準則を定められた場合には、普通地方公共団体の課税権は、これに従ってその範囲内で行使されなければならない。
法定普通税に関する条例において、地方税法の定める法定普通税についての強行規定の内容を変更することが同法に違反して許されないことはもとより、法定外普通税に関する条例において、同法の定める法定普通税についての強行規定に反する内容の定めを設けることによって当該規定の内容を実質的に変更することも、これと同様に、同法の規定の趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものとして許されないと解される。
(3)平成15年法改正の前後を通じて、特別の定めとして条例等により欠損金の繰越控除の特例を設けることを許容するものと解される規定は存在しない。
法人税法に規定する欠損金の繰越控除は、平成15年法改正前においては法人事業税の課税標準である各事業年度の所得の金額の計算について、平成15年法改正後においては法人事業税の所得割の課税標準である各事業年度の所得の金額の計算について、いずれも必要的に適用すべきものとされていると解され、法人税法の規定の例により欠損金の繰越控除を定める地方税法の規定は、法人事業税に関する同法の強行規定であるというべきである。
法人事業税の課税標準である各事業年度の所得の金額の計算においても、各事業年度間の所得の金額と欠損金額の平準化を図り、事業年度ごとの所得の金額の変動の大小にかかわらず法人の税負担をできるだけ均等化して公平な課税を行うという趣旨、目的から、地方税法の規定によって欠損金の繰越控除の必要的な適用が定められているものといえるのであり、このことからすれば、たとえ欠損金額の一部についてであるとしても、仮に条例において同法の定める欠損金の繰越控除を排除することは許されず、仮に条例にこれを排除する内容の規定が設けられたとすれば、当該条例の規定は、同法の強行規定と矛盾抵触するものとしてこれに違反し、違法、無効であるというべきである。
<金築裁判官補足意見>
2 原判決は、欠損金の繰越控除は、白色申告には認められていないし、過去にこれが認められていなかった時期もあったことなどから、この制度の採否や認める年限は立法政策により決め得ることで、他に選択の余地のない絶対的要請とまではいうことができないとする。この点は、原判決が、法律と条令の矛盾抵触は一方の目的や効果がその重要な部分において否定されてしまうことをいうとしているところなどと関係するものかもしれないが、そのような見解の当否はおくとしても、上記のような制度の採否等が立法政策事項であるからといって、その制度が重要でないことになるものではない。課税標準の定めなどは、ほとんどが立法政策事項であるといっても過言ではない。欠損金の繰越控除が認められるかどうかは、税負担に多大な影響を与えるものであって、このような事項が重要でないと考えることはできない。
4 法定税と課税標準が重複する場合であっても、当該地方公共団体における実情に即した、その税自体として独自の合理性が認められるものであれば、法定外税として許容される余地があるのであり、また、法定税と課税標準が共通性を有する場合などには税収や経済的効果において法定税に事実上の影響が及ぶことは避け難いのであるから、そのような事実上の影響があり得るとしても、法定外税が直ちに法定税と矛盾抵触することになるものではないと解される。 もっとも、国税や法定地方税が広く課税対象を押さえているため、これらの税との矛盾抵触を避けて、地方公共団体が法定外税を創設することには、大きな困難が伴うというのが実情かもしれない。しかし、憲法が地方公共団体の条例制定権を法律の範囲内とし、これを受けて地方自治法も条例は法令に反しない限りにおいて制定できると定めている以上、地方公共団体の課税自主権の拡充を推進しようとする場合には、国政レベルで、そうした方向の立法の推進に努めるほかない場面が生じるのは、やむを得ないことというべきである。
<検討>
1. 自主財政主義の意義
日本国憲法は、92条で地方自治の本旨について規定した上で、94条に条例制定権を規定するが、「これは、憲法が、明治憲法下の中央集権的・官治的な地方制度の否定のうえに立って、地方自治を保障し、地方団体に、その事務を、住民の民主的コントロールのもとに、自らの責任で自主的に処理する力を認めたことを意味する(※1)」。
「地方団体が、地方自治の本旨に従ってその事務を処理するためには、課税権、すなわち必要な財源を自ら調達する権能が不可欠である。それなしには、地方団体は結局において国に依存することになり、それと引換えに国の監督を受けることになりやすい。その意味で、地方団体の課税権は、地方自治の不可欠の要素であり、地方団体の自治権の一環として憲法によって直接に地方団体に与えられている、と解すべき」であり、「したがって、地方団体は、憲法上は、いかなる租税をいかなる課税要件のもとに賦課・徴収するかを自主的に決定することができる(※2)」。
「住民自治のもとでは、地方税の賦課・徴収は、住民の代表機関である地方議会の制定した条例の根拠に基づいて行われなければならない」が、「地方団体ごとに税制がまちまちになり、住民の税負担が甚だしく不均衡になるのを防ぐために、地方団体の課税権に対して国の法律で統一的な準則や枠を設ける(※3)」ため、憲法も「法律の範囲内で」(94条)と規定するが、「地方団体の自主性が十分に尊重されるべきであって、国の法律で地方税のすべてを一義的に規定しつくすことは適当でなく、また国の行政機関の指揮・監督権はなるべく排除する必要がある(※4)」。
ところで、小泉改革の中で平成11年に制定された地方分権推進一括法を受けて改正された地方税法は、法定外税について総務大臣の同意制度を採用したが、「総務大臣は、法定外普通税及び法定外目的税の新設・変更について、地方団体から協議の申出を受けたときは、(1)国税または他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となるとき、(2)地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること、または、(3)この2つの場合を除くほか国の経済施策に照らして適当でないこと、のいずれかの事由があると認める場合を除き、これに同意しなければならないこととされている。地方税法の法定税の規定は、強行規定であるから、その変更・修正を目的とする法定外税は違法である、と解すべきであろう(※5)」。憲法が「法律の範囲内で」条例制定権を認める規定ぶりである以上、強行規定に反する条例は租税法律主義違反といわざるを得まい。
本件で問題とされているのは、本件条例が、法人事業税の課税標準として規定される欠損金の繰越控除の一部を遮断する効果を持つため、法律上の強行規定に反して違憲であるのか(地裁・最高裁の立場)、法人事業税における欠損金の繰越控除規定は特例措置として許容されているにすぎず、強行規定とまでは言えないので、憲法違反とは言えないのか(交際の立場)という問題である。
2. 平成15年改正前地方税法72条の19の意義
いわゆる外形標準課税が法定化された平成15年度税制改正において、本件や東京都外形標準課税条例事件で利用された法人事業税の課税標準を条例によって変更できる旨を定めた地方税法72条の19は72条の24に改組されたうえ、課税標準の条例による変更の特例は廃止された。改正前地方税法では、事業の情況に応じ資本金額や売上金額等を課税標準とすることが認められていたが、平成15年度税制改正において、「都道府県の最大の税収減であった事業税の税収が激減」している状況に対応する一方で、「赤字法人に課税することは、不況対策に逆行して好ましくないという意見」も根強く、「この2つの意見の妥協の産物として、資本金額1億円超の法人の事業税について、所得に外形標準の要素(附加価値額および資本額)を加味する(※6)」外形標準課税を導入する際に、廃止されたのである。
この地方税法72条の19の特例の廃止については、衆参において「法人事業税について、現在収入金額を課税標準としている業種に関しては、今回の法人事業税への外形標準課税導入の趣旨にかんがみ、個々の地方公共団体に与える影響等も考慮しつつ、今後その課税の在り方の見直しに向けて、検討を行うこと(※7)。」との付帯決議があったこと、及び「付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって事業税を課する法人について、条例により所得以外の課税標準によって事業税を課することができる特例(旧地方税法72条の19)の適用の対象外とします(法72条の24の4)。なお、東京都及び大阪府における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例は、この旧地方税法72条の19の規定にものづくものです(※8)。」との地方税法改正の解説に着目すると、外形標準課税を地方税に導入したからには、所得に外形的な要素を反映させる役割を終えたものと捉えられたものと考えざるを得ない。したがって、平成15年改正法により、法人事業税の課税標準を変更する余地はなくなったとするべきであろう。
3.地方税法改正前に制定されていた条例が、地方税法の改正により廃止された規定に基づいて制定されていた場合における条例の適法性
地裁・最高裁の論理に則るとすると、本件条例は、法定税としての法人事業税の課税標準の中に存する欠損金繰越控除の効果を一部遮断するものであるから、そもそも違憲状態の条例であったものと考えられる。したがって、本件条例は、成立当初から違憲状態であって、総務大臣の同意がそもそも法解釈を誤ってなされたものと解すべきであろう。
一方で、高裁の論理に則るとすると、平成15年税制改正前に成立した条例であるから、神奈川県の財政上の必要から、法人事業税に類した法定外税を課したとしても、法人事業税の強行規定に該当する内容に抵触しない限り、地方団体の独自の判断を尊重すべきであるから、条例で課税することも許されることになろう。
まったく真逆の判断が示されたわけであるが、高裁がその沿革を踏まえて、法人事業税における欠損金の繰越控除制度を強行規定と捉えていないのに対し、最高裁は、金築補足意見にもあるように、「課税標準の定めなどは、ほとんどが立法政策事項であるといっても過言ではない。欠損金の繰越控除が認められるかどうかは、税負担に多大な影響を与えるものであって、このような事項が重要でないと考えることはできない」から、法人事業税の課税標準に密接に関係する強行規定であると捉える。
しかし、金築補足意見が「ほとんどが立法政策事項」だから「税負担に多大な影響を与えるもの」は強行規定だといってしまえば、条例制定権は不当に矮小に解釈されることになろう。本件においては、「国税または他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となるとき」に該当するかどうかを検討すべきであり、税負担が著しく過重になる租税公平主義違反が明らかな場合でなければ、地方団体の判断が尊重されるべき状況あったといえ、だからこそ総務大臣の同意を勝ち得たと考えるべきであろう。
4.地方税法改正前に制定されていた条例が、地方税法の改正により廃止された規定に基づいて制定されていた場合における条例を改正することの適法性
一方で、平成15年改正地方税法においては、法人事業税の課税標準を変更するための規定が外形標準課税導入の影響から廃止され、外形標準課税対象外の小企業にのみ適用される例外規定とされている。そのため、本件条例は、地方税法上に法律上の根拠を失った状態にあったといえよう。つまり、高裁の立場を採った場合においても、法改正後においても、本件条例の適法性が維持されているのか否かを検討せざるを得ない。
この点については、かねてより、次のような見解が解かれている。
「注意すべきことは、地方税について、国が法律によって、一方的に、地方団体に、特殊の産業に対する課税権を奪うことが適当かどうかということである。それは、いいかえるならば、国が地方団体に一定の政策を、地方税の非課税ということによって押し付けるという結果になるのであるからである。もとより、国といわず、地方団体といわず、国全体を通じて租税原則を超えて実施すべき政策があることは肯定しなければならないし、その場合においては、法律によって、地方団体の課税権を国が一方的に剥奪することも十分な理由があるとしなければならない。しかし、政府の立場においてする特殊政策の租税への導入…は、国の税法に規定されたからといって、当然に地方団体にそれへの順応を強いる必要はない。このような場合には地方団体自身において、その要否を判断すれば足りるのであり、国が必要をみとめない場合でも個々の地方団体においては、法6条の規定を適用する必要がある場合もあるのである。いずれにしても、このような、国、地方団体という立場を離れた、これを超えた国家全体の立場において要請される政策目的については格別、その他の場合について安易に租税原則に政策目的を導入することは、いわゆる租税政策の濫用であると考えられ、租税の基本原則である負担の衡平を著しく阻害するものといわざるを得ない。(※9 )
つまり、国の法律の改正により、地方税に影響を与える場合には、地方団体がその要否を判断すれば足り、その適法性に影響を与えないということである。
ところで、条例を改正せずにいればその適法性に影響を与えないとしても、条例を改正する場合には、その根拠法となる国の法律が改正されている以上、改正法の趣旨をかんがみる必要があろう。その内容に対する適法性を地方団体が判断するとしても、その手続については、改正法に従わざるを得ないであろうから、本件においては、条例改正に当たって、総務大臣との新たな協議による同意を得ることが必要であったと考えられるところ、本件条例は、新たな協議を持たなかったことを考えると、手続法上の不備があったと指摘されても致し方ない状況にあったといえる。また、法改正後の協議が行われた場合、本件改正に対する同意が得られたか否かも不透明であったといえよう。
したがって、裁判技術上の視点からは、法改正前については訴訟を提起せず、法改正後の条例改正を機に訴訟を提起したことが本件のポイントの1つであったとも考えられよう。いずれにせよ、平成15年税制改正により、法人事業税の課税標準に変更を加えることができなくなっているのであるから、今回の条例改正が、法人事業税の課税標準の一部を遮断する効果を持つことは明らかであり、違憲状態にあるといわれても致し方あるまい。
参考文献
- 金子宏『租税法〔第18版〕』弘文堂2013、89頁
- 金子、前掲書、89頁
- 金子、前掲書、90頁
- 金子、前掲書、90頁
- 金子、前掲書、91頁
- 金子、前掲書、528頁
- 『平成15年版改正税法のすべて』大蔵財務協会2003、745頁
- 『平成15年版改正税法のすべて』大蔵財務協会2003、761頁。なお、東京都外形標準課税条例事件においては、条例により変更された課税標準等の均衡が図れているかについて問題視された点には注意されたい。
- 柴田護・中西博・栗田幸雄・渡邊功『地方税総説』良書普及会1971、55頁
| 前へ | レポート・刊行物 目次へ |